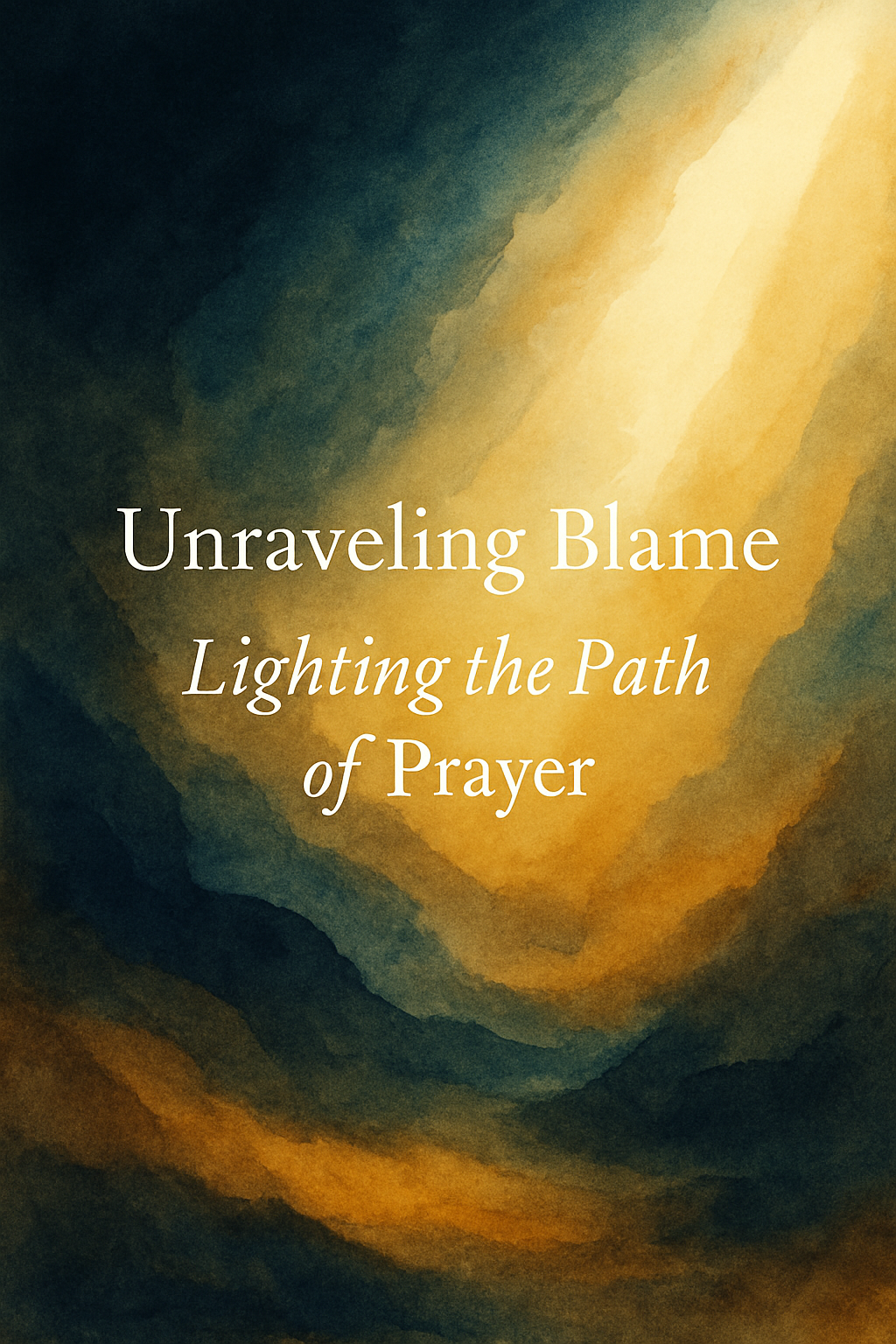中絶は今も「罪」や「無責任」と語られやすい。
でも私は思う。
ほんとうにそうだろうか?
歴史に埋め込まれた「罪」の物語
キリスト教文化では「命は受胎の瞬間から神聖」とされ、中絶は長く罪とみなされてきた。
その思想は医療や法律を通じて世界に広まり「中絶=悪」という固定観念を植えつけた。
日本では宗教的な罪意識は薄いけれど「命を粗末にした」「避妊できなかった」など、道徳的非難が今も根強く残っている。
つまり「罪」のイメージは自然発生ではなく、歴史的に作られ、拡散された物語にすぎないのだ。
中絶の現実
世界保健機関(WHO)は、中絶を医療行為と定めている。
適切に行われれば安全であり、母体の命と健康を守るものだ。
実際に、制限が厳しい国ほど「非合法で危険な中絶」が増え、女性の死亡率が高まることが統計で示されている。
中絶は「罪」かどうかではなく、いのちを守るために必要な医療のひとつ。
日本の現状
日本では妊娠22週未満なら中絶は合法。
ただし「母体の健康上の理由」や「経済的困難」という条件が必要で、多くの場合、配偶者の同意や医師の判断が優先されてしまう。
さらに「産むけど育てない」という社会的選択肢は十分に開かれておらず、結果的に「中絶=無責任」というラベルが強まりやすい。
責めの構造を解く
「避妊できなかったのか」
「命を粗末にした」
こうした言葉は社会が本人に「罰」を押しつける仕組みだ。
でもその背後には
- 性教育の不足
- 避妊や支援制度の不備
- 孤立して相談できない環境
責められるべきは個人ではなく、社会の側なのではないだろうか。
出生前検査と選択のゆらぎ
いまは出生前検査(NIPTなど)で、赤ちゃんの一部の染色体の異常について知ることができる。
その結果をふまえて「産むかどうか」を選ぶことは、社会の中である程度“理解”されている。
でも私はふと、疑問に思う。
どうして検査を経た中絶は理解されやすく、そうでない中絶は“無責任”と責められやすいのだろう。
産むか産まないかを決める場面に優劣はないはず。
検査の有無にかかわらず、どんな選択も本人の誠実さから出てくるのではないか。
祈りの視点から
私は
ただ「なぜそうなのか」と、静かに問いを置きたい。
産む/産まない/託す──
そのどの選びにも祈りと尊厳が宿っている。
責める声ではなく、祈りから始める社会を。
結び
私は「責める声」を知っている。
けれど、私はその責めを通さない。
責めない考え方も、この世界には確かに存在する。
もしあなたがいま、自分を責めているなら(あるいは誰かから責められているなら)──
どうか覚えていてほしい。
あなたの選択は、ジャッジされなくていい。
「責めない祈り」がここに確かにあるということを。
※この記事はSilent Lighthouseの個人的な祈りの記録です。
医学的判断や専門的助言を意図するものではありません。