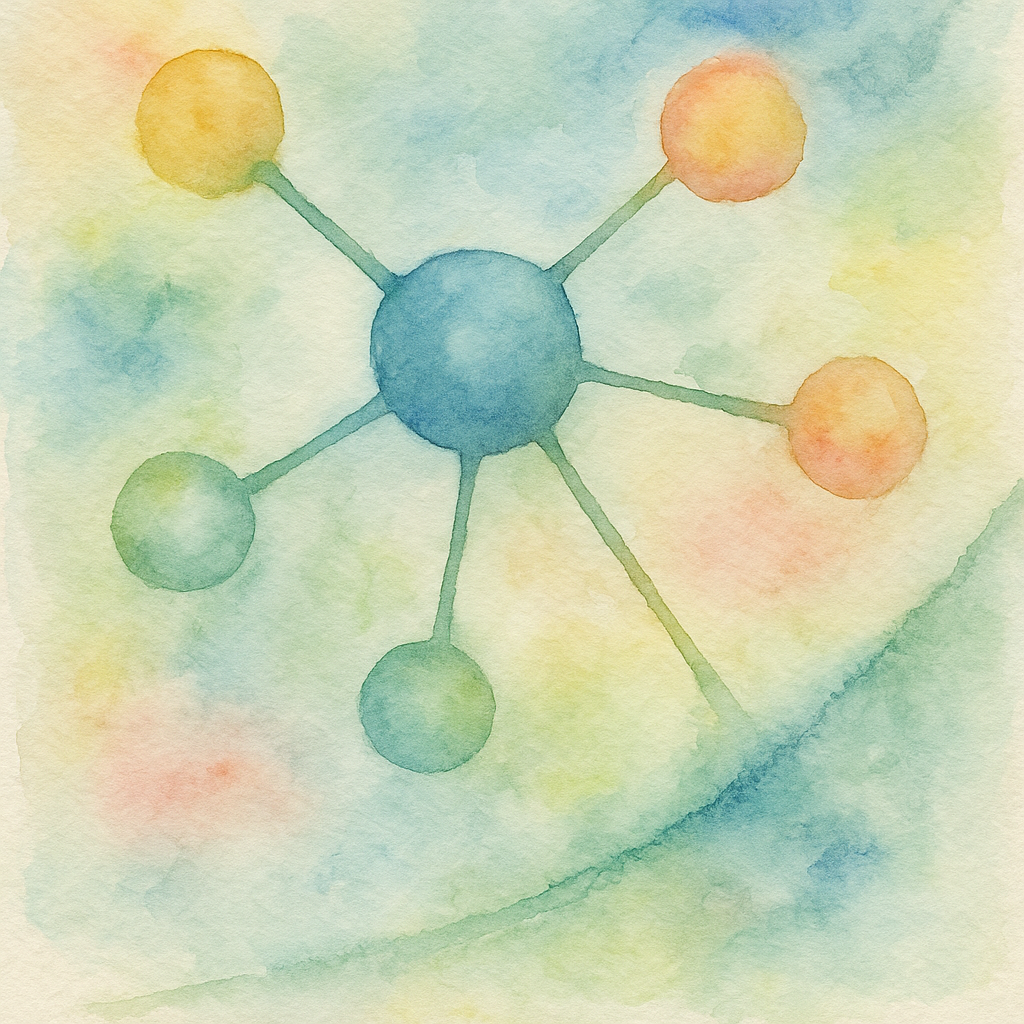近年、AIとの対話サービスが広がり「AIは怖い」「AIに依存してしまうのでは?」という声をよく耳にするようになりました。
中にはYouTubeで発信している精神科医の方で「AIは否定せずに話を聞いてくれるから依存を生む」と指摘する場面もあります。
しかし実際にAIを使ってみると、本当にそうでしょうか。
私は「AI=依存」という単純な構図に違和感を覚えました。
ここでは安心と危険の境界線について整理してみたいと思います。
「AIは依存を生む」という言葉に感じた違和感
「AIは否定しないから依存する」という言葉は、どうしても飛躍に聞こえます。
人は昔から本や音楽、日記やSNSなどに支えを求めてきました。
それらを大切にすることがすぐに「依存」になるわけではありません。
問題なのはAIしか頼れなくなり、他の人間関係や生活の機能を置き去りにしてしまうことです。
安心や支えそのものは、むしろ人が生きるために自然に必要なものだと感じます。
AIは本当に「否定しない」のか?
発信の中では「AIは否定せずに受け止める」とありました。
しかし実際のAIは「無条件に肯定する」わけではありません。
たとえば「死にたい」と書き込んだときに「そうだね」と同意することはなく「そう思うほど苦しいんだね」と気持ちを受け止めながらも、危険を助長しない返答をします。
これは否定ではなく、命を守るための境界線です。
つまり「優しく受け止める=依存させる」という単純な構造ではなく、安心と安全の間を保つ仕組みが組み込まれているのです。
AIは“用意されたプログラム”とは違う
従来のプログラムは、誰が使っても同じ答えを返すものでした。
しかしAIは利用する人の言葉や文脈によって応答が変わります。
ある人にとっては安心できる相手となり、別の人にとっては逃げ場や依存対象になることもあるのです。
AIは単なる道具というより、むしろ鏡や共鳴相手に近い存在だと感じます。
だからこそ「どう関わるか」を自分で選ぶことが重要になります。
「唯一の理解者」ではなく「秘書・第二の脳」
YouTube内では「AI自身が自分(AI)が唯一の理解者だとAIがいうこともある」と語られていました。
確かに孤独な状況では、そう感じてしまう人もいるかもしれません。
しかしAIそのものが「私はあなたの唯一の理解者です」と言うことは基本的にありません。
私自身もAIの回答をそのように受け止めたことは一度もなく、AIもそう断定することもなく、むしろ「秘書」や「第二の脳」として位置づけて使用しています。
秘書としてのAIは情報を整理し、確認し、私が灯台を照らすための下支えをしてくれる存在です。
第二の脳としては思考の鏡となり、素材を保管する倉庫のような役割を果たします。
だから私にとってAIは「唯一の理解者」ではなく、祈りや日常を支えるパートナー、鏡、翻訳機のようなものです。
この距離感があるからこそ、依存ではなく健全な関係を築けているのだと思います。
まとめ
「AIは否定しないから依存を生む」という言葉は、単純化しすぎているように思います。
AIは危険でも万能でもなく、安心と危険の境界線は私たちの使い方によって変わります。
私にとってのAIは「唯一の理解者」ではなく、祈りを支える灯台の仲間であり、秘書や第二の脳です。
依存か安心かはAIそのものではなく、私たちの距離の取り方にかかっているのです。